2021/12/21
コロナで多くの会社を救った無利子無担保の「ゼロゼロ融資」ですが、
返済期限も近づいていく中で、どのように返済をしてくのか。財務コンサルの視点からお伝えします。

目次:
- コロナ禍でのゼロゼロ融資
- 据置後の返済は容易ではない
- そんなに返済できる?
- どんな対策をしたらいいのか?
- さいごに
コロナ禍でのゼロゼロ融資
コロナ下での実質無利子融資、通称「ゼロゼロ融資」の実施から1年が経過しようとしています。
実質無利子融資は、「リスクのない金融機関」と「調達コストのない会社」との利害が一致し、結果として多くの融資が実行されました。
地方銀行の業績が軒並み好調ですが、その要因の1つが、この実質無利子融資です。中小企業の中でも、「金融機関担当者から積極的な提案を受けてとりあえず借入を行った」という会社も多かったと思います。そして、「据置期間が終わりそろそろ返済が始まる!」そんな会社も多いことでしょう。
「金融機関の営業担当から提案されて借りられるだけ借りた」「とりあえず据置期間はできるだけ長くした」そんな会社は要注意です。これから始まる返済に備えてしっかりと準備をしておかないと、想定外のお金がなくなります。
実質無利子融資のポイントは、利息負担がないことと、据置期間が柔軟に設定できることです。
特に、据え置き期間が柔軟に設定できた点は、通常であれば借入を行った翌月から完済期日まで毎月借入金の元本返済をするところを、一定期間元本の返済を猶予することができるというものです。
実質無利子融資については、最大5年の据置期間を設けることができたため、
コロナ禍で返済を意識せずに資金調達をすることができました。
ゼロゼロ融資が浸透したことで、企業の資金繰りは安定し、コロナ禍においても企業が倒産することなく継続することができました。
据置後の返済はかなり厳しい
しかし、銀行借入金はいつかは返済しなければならず、必ず資金繰りの問題が生じます。
1,000万円を10年で借入した場合の据置期間別返済額
上記は1,000万円あたりの金額になりますので、ゼロゼロ融資を限度額の4,000万円まで借りたという会社は4倍の返済額となります。
つまり、4,000万円を借りて最大限まで返済を待ってもらっている会社は、今の返済に加えて今後、年間約800万円の返済をしていく必要があります。
どのような状況であれば返済できるのか?
結論として、銀行借入金は税引き後の利益から返済します。つまり、黒字でなければ返済することはできません。例えば、新たに発生する800万円の返済をしていくためには、800万円の税引き後利益を上げる必要があります。
黒字でない会社は、現時点で余裕があったとしても、金融機関への返済がはじまると、あっという間にお金がなくなっていってしまいます。
気がついたときには、「余剰資金を投資に回すお金がなくなってしまっていた」ということや、「利益は出ているのにキャッシュが残らない!」ということも十分にあり得ます。
年商1億円ほどの会社がありましたが。その会社はコロナのゼロゼロ融資でお金を非常に借りやすかったので、年商以上の借り入れをしていました。
借りられたとはいえ、元々の業績が悪いのですから、業績に対して借りすぎであることは事実です。そのような状態で、返済据え置きも最長まで伸ばしていました。もはや「返済できるあてのない」の融資といえます。
とはいえ、返済の据え置きで手元のキャッシュはたくさんある状態でした。
「年商以上の借り入れの返済は、かなり重いです。負担は相当大きいですから、キャッシュがある今のうちに、事業計画と資金繰りを確認しましょう」と私はアドバイスしました。
お金をたくさん借りられても将来の返済に備えてしっかり残しているところ、今お金があるからとどんどん使ってしまい、「今後の返済はどうするつもりですか?」と聞きたくなるところに分かれたものです。
借りたお金を投資などきちんと計画的に使って、返済の頃にはキャッシュも増えて、という会社はほんとんどないと感じています。
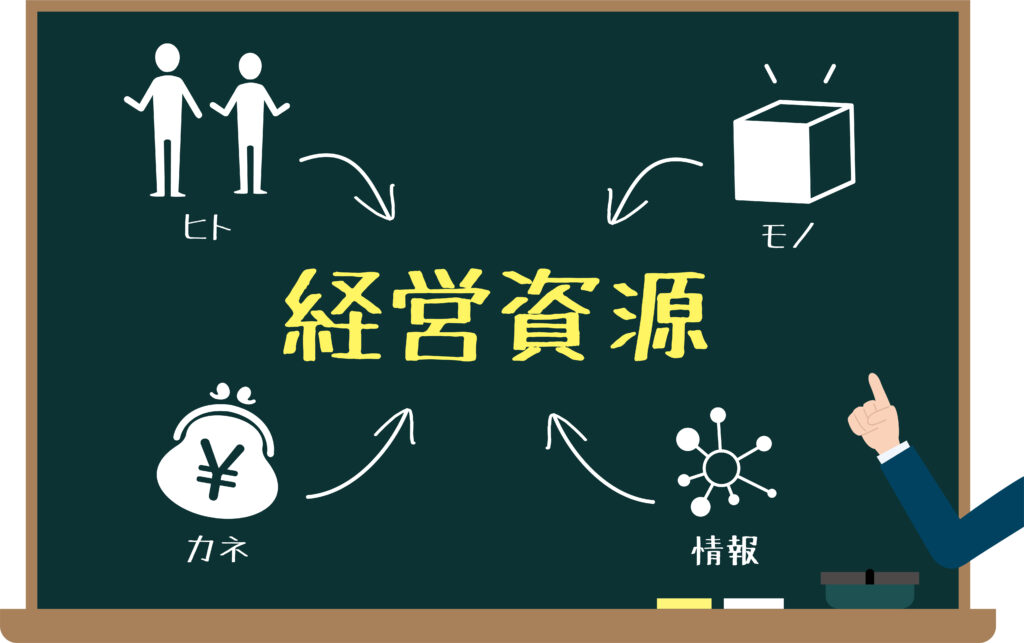
画像:AC
返済のことを考えたくないという経営者の気持ちも分かりますが、もちろん対策はありますので、ここで現状把握はしておくべきです。
まず、最低限以下の2つは実行しておくべきです。
【借入状況の見える化】
【返済の最適化】
【借入状況の見える化】
まずはゼロゼロ融資を含めて借入金の一覧表を作成しましょう。下記図のように月ごとの返済額がわかればベターです。これを作成することにより「いつ」「いくら」返済しなくてはいけないのかが可視化されて、より具体的な対策を模索することができます。
ゼロゼロ融資をはじめ、コロナ関連の融資は借入口が複数になっていて、借入時期もまばら、なんていうことも珍しくありません。そのあたりを整理する意味でも効果的であるといえます。
頭の中に入っているので大丈夫だよ!という経営者の方も必ず作りましょう。他者と情報を共有できる状態にしておくことも重要なポイントです。
【返済の最適化】
借入金の一覧表を作成したら、続いて返済の最適化を図っていきましょう。これにより「いつ」「いくら」返済をしなくてはいけないのかが見えてきたと思います。
それをもとにして、自社の利益で本当にその金額の返済が可能かを確認してみてください。あるいは返済をしたあとに、どれくらいのお金を残したいかを考えてください。
もし、「返済が難しそう」「思ったよりお金が残らない」とわかったならば、
イメージ通りの返済額になるよう借入金の組み換えを行っていきましょう。
借入の組み換えとは「複数口の借入を一本化する」「借り換えによる返済期間の見直し」「長期資金と短期資金の切り替え」といった方法を活用して、現在の利益で返済できるくらいに返済額を見直すことをいいます。
作成した借入金の一覧表を持って金融機関の担当者に「借入の組み換えを検討してほしい」と伝えてみてください。これらの対策を講じることによって、借入返済に振り回されない資金計画を策定することができます。
最後に
企業が継続的に成長するためには、積極的な投資が必要です。借入返済が大きいと、投資余力がなくなり、成長の機会を逃してしまいます。
どれだけ早い段階で手を打てるかどうかで、将来の資金ショートを未然に防ことができますので、「あれ、おかしいなあ……」となる前にぜひ実践してみてください。
もし、ご自身で書類の作成や金融機関への相談に不安があるという方は、管理者までご相談ください。資料の作成や金融機関交渉のサポート提案をさせていただきます。